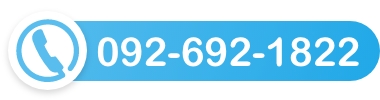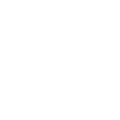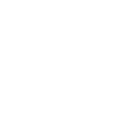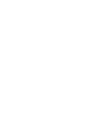福岡宇美町の一般内科 糖尿病内科 漢方内科「まき内科」
漢方内科
一人ひとりに合ったオーダーメイドな漢方治療
漢方医学には、「中庸:個人のバランスの取れた本来の状態」という考え方があります。漢方診療においては、患者さんの体質、症状、診察所見から病気の全体像をとらえ、からだ全体の不調和を「中庸」に戻すことを目標としています。
当クリニックでは、漢方診療独特の診察を行い、からだの不調の原因を探り、一人ひとりに合ったオーダーメイドな治療を提供します。漢方薬=万能薬ではありませんが、人が本来持つ「治(なお)そう」とする力を引き出すことができます。西洋医学的に診断できない、あるいは西洋医学的な治療では十分な効果が得られない身体・精神的な不調も漢方医学的治療が有効な場合が多々あります。
今までお悩みの体調不良に関して、一度ご相談ください。
当クリニックでは、漢方診療独特の診察を行い、からだの不調の原因を探り、一人ひとりに合ったオーダーメイドな治療を提供します。漢方薬=万能薬ではありませんが、人が本来持つ「治(なお)そう」とする力を引き出すことができます。西洋医学的に診断できない、あるいは西洋医学的な治療では十分な効果が得られない身体・精神的な不調も漢方医学的治療が有効な場合が多々あります。
今までお悩みの体調不良に関して、一度ご相談ください。
診療の流れ
漢方医学で重要な診察方法である四診(※)を行い、患者さんごとの情報を抜き出し、処方する漢方薬を選んでいきます。
必要に応じて、電気温鍼(冷えの状態を確認する検査)を行います。
必要に応じて、電気温鍼(冷えの状態を確認する検査)を行います。
※四診:漢方医学で用いる4つの診察方法、「望診」「聞診」「問診」「切診」のこと
STEP
望診
患者さんを見て、顔色や立ち振る舞い、皮膚や爪の状態をみます。切診の時に、舌の色・形・苔の状態を確認します。
STEP
聞診
声の調子、話し方、お腹の調子などを確認します。
STEP
問診
暑がりなのか寒がりなのか、汗の有無、尿や排便の回数、疲労や驚きやすさ、どのような状況で症状が悪化するか、などをお伺いします。(※診察前に、問診票をお渡ししますので、記載をお願いします)
STEP
切診
手首の橈骨動脈に触れ(脈診)、お腹の診察(腹診)をします。
電気温鍼について
背中のツボに鍼(はり)を打ち、その上から電気温熱器で温め、冷えの程度をみる検査です。検査以外に治療にも使います。冷え症、肩こり、腰痛など温める事で症状を改善させます。

漢方薬について
漢方薬には2種類あります。
当クリニックでは、多くの医療機関で処方されているエキス製剤(粉薬)や丸薬だけでなく、煎じ薬(生薬)も揃えています。
それぞれ一長一短があり、どちらでも自由に選択できます。診察時に相談しながら、決めていきましょう。
当クリニックでは、多くの医療機関で処方されているエキス製剤(粉薬)や丸薬だけでなく、煎じ薬(生薬)も揃えています。
それぞれ一長一短があり、どちらでも自由に選択できます。診察時に相談しながら、決めていきましょう。
エキス剤
エキス剤とは、煎じた生薬の液体成分からそのエキスを抽出し、顆粒や粉末などに加工したものです。効果の面で煎じ薬にやや劣るものの、携帯性や保存性に優れています。
煎じ薬(生薬)
煎じ薬(生薬)は、自然界に存在する動植物・鉱物の薬効部位を使った薬のことです。煎じ薬は生薬の力を最大限に引き出すことができ、かつ生薬の分量を患者さんごとに調整できる点が最大のメリットです。煎じる時間など手間がかかります。

漢方治療が有効な症状や病気
下記のような症状や病気が対象となりますが、その他に気になる症状があれば、一度ご相談ください。
漢方薬単独あるいは西洋薬も併用しながら治療にあたります。
漢方薬単独あるいは西洋薬も併用しながら治療にあたります。
小児
漢方薬は飲めるお子さんとそうでないお子さんがいらっしゃいます。まずはご相談ください。
主な症状
起立性調節障害:朝調子が悪い、朝起きれない
湿疹(アトピー性皮膚炎)
夜尿症:おねしょ
食欲不振、腹痛(主に過敏性腸症候群)、下痢、便秘
頭痛
冷え性 など
湿疹(アトピー性皮膚炎)
夜尿症:おねしょ
食欲不振、腹痛(主に過敏性腸症候群)、下痢、便秘
頭痛
冷え性 など
成人
主な症状
全身倦怠感、疲れやすい、肩こり
頭痛:特に天候、気圧、冷え、ストレスにより誘発されるもの
冷え、冷えによる諸症状(痛み、倦怠感、しもやけ、お腹が冷たい)
消化器症状(胃部不快感、食欲不振、腹痛、下痢、便秘)
月経不順、月経痛、更年期障害、のぼせ
浮腫
不眠、不安感、抑うつ気分(うつ病などはっきりしたものがあれば心療内科や精神科と併診が必要です)
めまい
湿疹、アトピー性皮膚炎
動悸
肥満
口腔内乾燥(口が渇く、唾液が出ない)
腰痛、膝痛、関節痛(へバーデン結節など)
神経痛(三叉神経痛、帯状疱疹後神経痛、坐骨神経痛など)
繰り返す膀胱炎 など
頭痛:特に天候、気圧、冷え、ストレスにより誘発されるもの
冷え、冷えによる諸症状(痛み、倦怠感、しもやけ、お腹が冷たい)
消化器症状(胃部不快感、食欲不振、腹痛、下痢、便秘)
月経不順、月経痛、更年期障害、のぼせ
浮腫
不眠、不安感、抑うつ気分(うつ病などはっきりしたものがあれば心療内科や精神科と併診が必要です)
めまい
湿疹、アトピー性皮膚炎
動悸
肥満
口腔内乾燥(口が渇く、唾液が出ない)
腰痛、膝痛、関節痛(へバーデン結節など)
神経痛(三叉神経痛、帯状疱疹後神経痛、坐骨神経痛など)
繰り返す膀胱炎 など